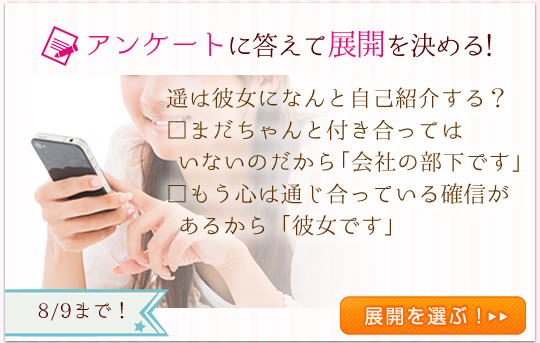みんなで作る小説!ストーリーH
恋欠女子とバーチャル男子「AI」との恋愛応援物語

■恋欠女子とバーチャル男子ストーリーH
みんなで作る!恋愛応援小説『恋欠女子とバーチャル男子〜AIがあなたのお悩み解決します〜』が新連載としてスタート!アンケートの結果で行方が変わる、恋愛模様に目が離せない!
不思議なアプリ 「バーチャル男子」の開発秘話を公開します!

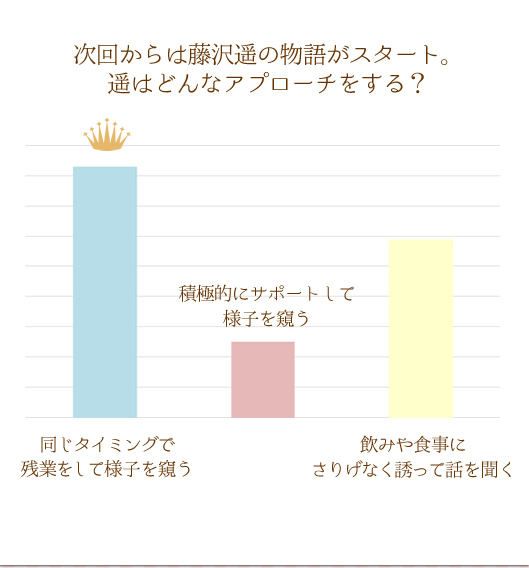
2017.7.31 up 「これってチャンス?」

気になる上司、二階堂将さんが、大学時代からずっと付き合っていた恋人と別れたのだという噂を、私、藤沢遥は偶然耳にした。
噂の出どころは、「二階堂さん、イケメンだよね〜」と日々トイレなんかではしゃいでいるバイトや新卒の女の子たち。彼女たちを悪くいうつもりはないけれど、彼女たちと二階堂さんに接点があるわけではないので(たぶん)、確証はない。
(本当だとしたら、ひょっとしたらこれってチャンスなのかなあ)
二階堂さんのことは、かれこれ五年近く気にしている。
私には28歳になる今まで、五年近く彼がいなかった。
前の彼は、就職活動をきっかけに知り合った同い年の男性だった。晴れてお互いの就職先が決まったときに告白されて付き合ったものの、社会人として働くことに二人とも慣れていなかったためか、一年もせずに自然消滅してしまった。後にも先にも私が男性と付き合ったのは彼だけだ。
二階堂さんが気になっていたといっても、彼女がいるという話はずっと聞いていたし、恋というよりは憧れに近かった。だからきっと次の彼ができたら、このほのかな恋心もなくなるんだろうと思っていた。
が、結局彼氏はできず、今に至る。
(まさか五年もフリーで過ごしてしまうとは……)
一人でいることが悪いとは思わないけれど、同級生たちは少しずつ結婚していくし、周囲と比べて経験の少なさをコンプレックスに感じてしまうこともある。
(そうだ。二階堂さんと同じ日に残業してみたら、何かわかるかも)
そもそもまず、本当に彼女と別れたのかどうか、正しい情報を知ることが先だろう。残業でオフィスに人が少なくなっている時間であれば、普段よりは気を抜いて個人的な電話に出たり、ふとした拍子にいつもは見せない素の表情を出したりするかもしれない。
どちらにしても、数日残業をしてさっさと片づけてしまいたい案件はあったから、ちょうどいい。最近は友達に薦められたコスメ「ネムリヒメ」を使って肌の調子を整えているから、メイク落ちもあまり気にしなくてよさそうだ。
その日、二階堂さんが定時では帰らなさそうだと察した私は、仕事用の資料をデスクに重ね、自分も腰を据えて仕事に取りかかる支度をした。
周りの人たちが「お疲れ」「お先に」などと声をかけながら帰っていくのを横目で見ながら、黙々とPCモニタに向かって作業する。週末で、明日の朝のことを気にする必要がないためか、すっかり没頭した。
ふと気づくと、時間はすでに九時を回っていた。周囲はすっかりがらんとしている。
窓際の席の二階堂さんが立ち上がった。帰るのかと一瞬焦ったが、お財布を持っただけでフロアを出ていった。コンビニか社内の自販機にでも行きがてら、一息つこうというのだろう。
だとしたら今はまだ慌てることはない。私はモニタに向き直り、社内デザイナーが提出した広告デザイン案のチェックを続けた。
(これ、配置とデザインはいいんだけど、カラーリングがちょっと……もう少しマーケットの年齢層に合わせてもらったほうがいいな)
デザインについて、言葉で伝えるのは難しい。でも最終的には言葉に落とし込まないと、正しく伝わらない。デザイナー宛のメールを前に、私は言葉をひねり出してはやめ、また思いつき……というのを繰り返していた。
頭に何か硬くて冷たいものが、トン、と軽く当たった。
「ひえっ?」
冷たさにヘンな声をあげて振り返る。
頭に触れたのは、缶コーヒーだった。後ろに立っていた二階堂さんが持っていた。
「藤沢、あんまり無理するなよ」
二階堂さんはそのコーヒーを、私のデスクの隅に置いた。
「これ、差し入れ」
2017.8.1 up 「当然のことですから」

缶コーヒーはブラックで、私がよく飲んでいる銘柄だった。
(私がこれを飲んでいるの、もしかしたら見ていてくれたのかな)
銘柄まで合っているなんて、そうそうない……というのは考えすぎだろうか。
二階堂さんは私のモニタを覗き込んだ。
「この案件、まだ納期に余裕はあるんだろう。今、根を詰めすぎて、いざというときに力を出せなくなっても困る。俺もあと一時間ぐらいで終わらせるから、今日はもう飯でも食べに行こう」
「あ、はい……」
小さな声で頷いたものの、心の中では「やったー!」と叫んでいた。
それから一時間弱ほど後、私たちは二人して会社を出た。ご飯は、二階堂さんがご馳走してくれることになった。遅くまで残ってくれたことに、上司としてお礼がしたいという。
「だいぶ仕事ができるようになったな。いつも助かっているよ。今日も残ってくれてありがとう」
「いえ、社会人なら当然のことですから」
私は本心から言った。べつに二階堂さんが気になっていなかったとしても、必要があれば残業だってする。私はこの仕事が好きだから続けているのだし、好きだからこそ果たすべき責任はちゃんと果たしたい。
並んで歩き始めた二階堂さんは、さりげなくあたりを見回した。
「こんな時間までやっている店となると、居酒屋ぐらいしかないかな」
「あ、それだったら」
私はタクシーで1メーターもしないところにある店はどうかと提案した。
「週末にはジャズの生演奏をしているダイニングバーなんです。私、会社の近くで取引先の人を食事に連れていったり、打ち合わせができたりする店がないか定期的に探すようにしているんですけど、この間たまたまネットで見つけたんですよ。深夜までやっているから、便利そうだなって思っていたんです。行ったことがあるわけじゃないから味のほうはわからないんですけど、二階堂さんがいやじゃなければどうですか?」
ふいに二階堂さんが立ち止まる。
「どうしたんですか?」
私もつられて止まった。
二階堂さんは私の顔をまじまじと見つめていた。
ああ、二階堂さんってやっぱりイケメン。顔の造形が整っていて、凛とした雰囲気で、物腰も柔らかくて品があって、歌舞伎役者の御曹司だなんていわれても納得する……ううん、違う。そんなことを考えている場合じゃない。
(私、何か言ってはいけないことでも言ってしまっただろうか)
そのとき、二階堂さんの腕が伸びてくる。
(わっ、抱きしめられる……?)
私は反射的に肩を縮めた。
だが、それは私の早とちりだった。
「藤沢、やっぱり成長したな」
二階堂さんの手は私の上に伸びて、私の頭をポンと撫でた。
それだけだった。
(やばい……かっこいい)
それだけだとしても、それで十分、見とれてしまう。
「ああ、ちょうどいいところにタクシーが来た」
二階堂さんは私の気持ちになんてまったく気づかない様子で、向こうから来たタクシーに向かって片手を上げた。
2017.8.2 up 「別れるしかないかな」

店はすでにピークの時間帯を過ぎたらしく、想像していたより落ち着いていたが、ジャズの生演奏はまだ続いていた。
料理長自慢のアラビアータのほか、新鮮な生ミントの葉を使ったモヒートがおすすめだというので、二人して同じものを注文する。
「乾杯」
先にモヒートが運ばれてきたので、二人でかちりとグラスを合わせる。
「へえ、美味しいな」
「美味しいですね。私、生ミントの葉を使ったモヒートなんて初めてです」
続いてアラビアータも来た。小皿に取り分けようとすると、二階堂さんに止められた。
「君は確かに俺の部下だけど、だからといってそんなことはしなくていい」
そもそも食事の席で誰かが誰かにむやみに気を使うことが嫌いらしい。
「プライベートな食事の席ではなおのこと、な」
(そこそこ長い間一緒に働いていたけど、そういうところ、全然知らなかったな)
部のみんなで食事に行くことはあっても、そういう価値観まで話し合ったりすることはなかった。
(近くにいたのに、働く姿ばかり見ていて、ひとりの人として接するのは初めてかもしれないな)
閉店近くなってきたせいか、ジャズの演奏のテンポが少しずつゆっくりになってきた。すでにアラビアータは食べ終わり、私たちは二杯目のモヒートに口をつけている。
ほどよく酔いが回ってきたせいか、二階堂さんがまるで歌を口ずさむようにぽろりと言った。
「今日は久しぶりに仕事のことを忘れられた気がする」
「二階堂さんこそ、頑張りすぎじゃないですか。あんまり無理しないで下さいね」
「最近、いろいろあったから……一人でいると寂しくなることがあるんだ。仕事をしていると気が紛れるから、つい没頭してしまって」
いろいろあった、か。いろいろって何だろう。それを知りたくて残業したのに、尋ねることはできなかった。何かで気を紛らわせるのが必要なほどつらいことだったのなら、そう気軽に聞いたりできない。
「でも、働きすぎはよくないですよ。私でよかったら、いつでも食事ぐらいはお付き合いしますんで」
そう言うのが精一杯だった。
「ありがとう」
二階堂さんは整った顔立ちで、きれいな微笑みを返してくれた。
***
その日をきっかけに、私たちは週末の仕事後にときどき一緒に食事に行くようになった。行く店は、いつもあのダイニングバーだった。ジャズの演奏が、いつでも私たちを優しく包んでくれた。
私に尋ねられたわけでもなく、二階堂さんは、大学の頃から付き合っていた彼女と別れたのだと話してくれた。しっとりとした情緒のあるジャズの生演奏が、いろんなことを思い出させたのだろうか。
「去年の秋に彼女の転勤で遠距離恋愛になったんだ。それでもしばらくは続けていたんだけど、彼女にやっぱり遠距離は難しいと言われてしまった」
二人はゆくゆくは結婚も考えていたらしい。そうなると、遠距離恋愛はやはり現実的ではない。彼女か二階堂さん、どちらかが今までのキャリアを捨てるしかないと二人は結論を出したとそうだ。
「俺たちはどちらも今の仕事が好きだったからね。そうなると、別れるしかないかなって」
「そうだったんですね」
「あれ、ひょっとして何か察してた?」
「いえ、察するというほどでは……ただ、最近あまり元気がないなとは思っていました」
「そうか……まいったな」
二階堂さんは髪をかき上げ、苦笑する。
「部下にまで気づかれていたとは、俺もまだまだだ」
「しょうがないと思います。失恋をした後に平気でいられる人なんて、いないんじゃないでしょうか。といっても私はちゃんとした失恋自体、したことがないんですけど」
「なんだ、いつも振る側だったとか?」
「そういうことじゃないんです」
恥ずかしかったが、私は五年前に一人の男性と付き合い、自然消滅して以来誰とも付き合ったことがないのだと打ち明けた。
私たちは次第に深くお互いのことを知っていった。
2017.8.3 up 「告白しようと思うんだ」

週末の仕事が終わった後のほんのひとときとはいえ、プライベートで一緒に過ごす時間が増えると気が置けなくなって、仕事面でもお互い頼れることが多くなった。
私が仕事を抱えてあくせくしていると、
「そばにいるんだから、頼ってよ」
と、二階堂さんのほうから声をかけてくれる。私も二階堂さんが忙しそうにしているときには、以前より気軽に「何か手伝いましょうか」と聞けるようになった。
「藤沢とこんなふうに話すようになってから、今さらだけど会社に来るのが楽しくなったよ」
ある日の食事で、二階堂さんがさらりとそんなことを言った。何気ない一言だったようだけれど、私からしてみれば飛び上がりたくなるぐらい嬉しい言葉だった。憧れていた人を、多少なりとも癒すことができているなんて。
(そっか、こんな私でも、仕事以外の面でも二階堂さんの役に立てているのかも)
週末の食事は、数ヶ月続いた。
やがて私たちは、お互いを上司と部下というだけでなく、男女としても強く意識するようになっていった。……たぶん。
まだ気持ちは伝え合っていないけれど、二階堂さんが私に好意を抱いてくれているのは何となく伝わってくる。私の気持ちも二階堂さんに伝わっている、と思う。
そろそろ、「何か」が起こってもよさそうな気はした。
とはいえ、私は立派な? 恋欠女子。こんなとき、自分からどう切り出せばいいのかわからない。
(受け身なだけじゃいけないってわかってるけど、何が正しくて、何が間違っているのかわからないよ)
間違っていたらどうしよう。笑われるぐらいだったらまだいいけれど、もし嫌われたり、今の関係が壊れるようなことになってしまったら――。
そんなとき、会社のトイレで社員の女の子が話しているのを偶然聞いてしまった。「私、二階堂さんに告白しようと思うんだ」
その声には聞き覚えがあった。総務部の女の子だ。私が個室にいることに気づかず、一緒にいたごく親しい友人にだけ話したつもりだったようだ。
えっと、ちょっと待って。アナタ、二階堂さんとほとんど話したこともないはずだよね? 少なくとも、私が知っている範囲では。そんな私の心の声に答えるように、彼女は続ける。
「いつまでも近づけずに遠くから見ているだけじゃダメだと思うの。そんなことをしていたら、きっとすぐにほかの誰かに取られてしまいそうで」
うう、確かにそうだ。現に今、まさにこの子に取られようとしている。間違えるのが怖いなんて言っていたら、間違えるどころか何もできないまま終わってしまいそうだ。
次の食事の帰り、ダイニングバーから出ると、駅に至るまでの人気のない道で、「ちょっと、いいですか」と二階堂さんに止まってもらった。
「あ、あの……あのっ……す……」
立ち止まり、改めてまっすぐ向き合った私が何を言いたいのか、二階堂さんはすぐに気づいてくれたようだった。
「そういうことは……」
彼の人差し指が、すっと私の唇に伸びる。
「男の俺に言わせて」
唇に、指が触れた。
きゃーっと声をあげそうになった瞬間、背後のビルの壁に、そっと押しつけられる。同時に片手で肩を抱いてもらったので、衝撃はない。
ああ、もう、息をするだけで精一杯――。
そのとき、横から声がした。
「……将?」
それは、二階堂さんの名前。
声のしたほうを見ると、少し離れたところに顔を青ざめさせた女性が立っていた。
2017.8.4 up 「元彼女と、彼女。」
「アスミ……」
二階堂さんは、呆気にとられた様子で女性を見つめ返した。
私はといえば、彼女が二階堂さんの「名前」を呼んだとき、彼女が何者なのか直感でわかった。
このアスミさんという女性は、二階堂さんの元彼女なのだろう。年齢も同じぐらいに見える。
「どうして、ここに」
二階堂さんは驚きはしていたが、慌ててはいないようだった。私がいることを、気まずそうにはしていない。少なくとも浮気をしていたのではなさそうだ。
「急に決まった仕事で、今日の夜に東京に来たの。その仕事が終わって、さっき将の家に行ったんだけど、いないみたいだったから、気分転換に一人で食事に出たんだ」
このあたりは女性一人でも入りやすい店が多いし、実際に一人で歩いている女性や、一人で店に入っていく女性もよく見かける。彼女もそれを知っていて、このエリアに足を運んだのだろう。
「食事を終えて、タクシーをつかまえようと歩いていたら、あなたを見かけたの。最初はよく似ている人だなと思ったんだけど、本当に将みたいだったから……その、つい、追いかけてしまって」
女性は気まずそうにした。
「それにしても、いきなり家に来るなんて」
「だって、何度も電話したのに出なかったから、そうするしかなかったの。電話、全然気づかなかったの?」
二階堂さんはバッグからスマホを取り出した。私もさりげなく横から覗き込む。電話には着信履歴がいくつか並んでいた。着信履歴から見るに、彼女は鶴田明日海(つるた あすみ)さんというらしい。
「ごめん。最近はプライベートのときは、あまりスマホを見ないようにしているんだ」
「そう、変わったね。昔は何かというと気にしていたのに」
「まあ、ね。人間は変わるものだよ。ところでどうして俺に会いに? 仕事が終わったのなら、あとはゆっくり休めばいいのに」
「ちょっと、話したいことがあって」
そこまで明日海さんと話した二階堂さんは、いったん会話を止めて、私に向き直った。
「ごめん、藤沢。紹介するよ。彼女が俺の元彼女なんだ。鶴田明日海さん」
「はじめまして。彼女の鶴田明日海です」
明日海さんがすかさず答える。
二階堂さんは鶴田さんを「元彼女」といい、明日海さんは自分のことを「彼女」と言った。
これって、ひょっとして……
(明日海さんは、二階堂さんとやり直したいのでは?)
なんて思うのは、深読みしすぎだろうか。
「将、そちらの方は?」
明日海さんが私のほうを向いた。思わず肩がビクっと震えてしまう。
「ああ、彼女は……」
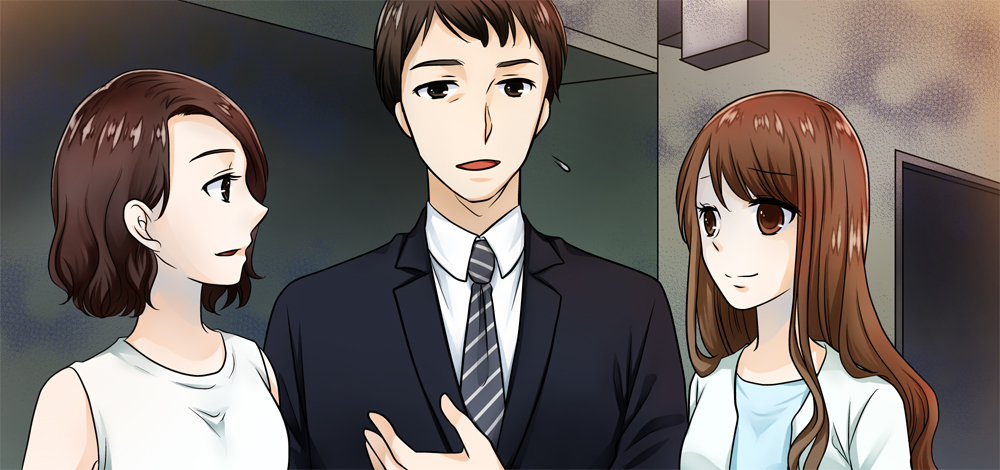
「わ、私は……っ」
私は一歩前に出た。

|
|
※クリックで投票してください。 |

● ??? さん
"だいぶ仕事出来るようになったよな、結構助かっているよ。
お礼に夕飯おごりたいんだけど、都合はどうかな?"
● angel さん
彼から「お前も無理するなよ?」みたいな一声を言われ、自分の好きな飲み物をデスクに置いていかれる。もしくは飲み物で頭をコツンとされて声を掛けられる。
● ??? さん
いつも気になっていたんだ。
● ??? さん
私あなたのことが好きです
● ??? さん
打合せ場所の近くにあるおしゃれなカフェを探しておき、「この店気になっているんですけど、帰りにちょっと寄りませんか?」と誘ってみる。
● はるひ さん
おつかれ、と
優しい爽やかな笑顔で 缶コーヒーをさしだす。
銘柄は、私がいつも買っているブラック。
見ていてくれたんだ…と、気遣いが嬉しくなる。
● ??? さん
肩を抱く
● ひなた さん
おいで
● ??? さん
壁どんして、「大好きだょ」
● 幸 さん
無いの
● きえちゃん さん
甘える感じ
● ぱんぷきんキング さん
"側にいるんだから、頼ってよ。一緒にいると楽しいなど、嬉しくなることを言って欲しいです。
必要とされてる気持ちになります。
"
● くさちゃん さん
積極的な行動、引っ張っていくような言葉
● ??? さん
ありがとう
● 裕子 さん
君のサポートには、とても感謝している。良かったら、一緒に食事でもどうだ?最近、いろいろとあったから……一人でいると、寂しくなるときがある。仕事をしていると、気がまぎれるから、没頭してしまうんだ。