
�݂�Ȃō�鏬���I�X�g�[���[B
�������q�ƃo�[�`�����j�q�uAI�v�Ƃ̗�����������

���������q�ƃo�[�`�����j�q�X�g�[���[B
�݂�Ȃō��I�������������w�������q�ƃo�[�`�����j�q�`AI�����Ȃ��̂��Y�݉������܂��`�x���V�A�ڂƂ��ăX�^�[�g�I�A���P�[�g�̌��ʂōs�����ς��A�����͗l�ɖڂ������Ȃ��I
�s�v�c�ȃA�v�� �u�o�[�`�����j�q�v�̊J����b�����J���܂��I

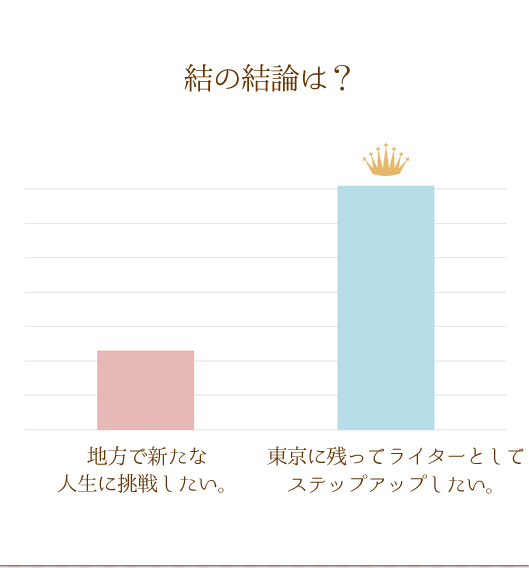
2017.3.6 up�@�u�����ƁA�����Ɛ́c�c�v

�����ŃX�e�b�v�A�b�v��ڎw�����A�n���ŐV���Ȑl���ɒ��킷�邩�\�\�B
�u���S�ݓX�̂������ʔ̃T�C�g�c�c���B���߂�A�l����̂ɏ������Ԃ�������Ă����H�@���������E����b�ɂȂ肻�������v
�@�����q�˂�ƁA�j�c����͐^���ȕ\��œ������B
�u�������A�����ɕԎ������炨���Ƃ͎v���Ă��Ȃ���B�ꃖ�����炢�͗P�\�����邩�����̂Ȃ��悤�ɍl���Ăق����v
�@�����ɒ����ƁA�Ƃ̍Ŋ��w�܂Ő��w�̂Ƃ���ŎԂ���~�낵�Ă�������B
�u�f�[�^���ł�����ɐ삳��ɂ������B�����ɂȂ�Ǝv���B���Ⴀ�A�����v
�u�����l�ł����v
�@���U���ĕʂꂽ�B
�@�����A�j�c���瑗���Ă����ʐ^�������e�����������Ă���A�{�i�I�ɍl�����B
�@���āA�ǂ����邩�B
�i����ȂƂ��́A�s�����Ă݂悤�j
�@�Y������Ȃ�����ǁA���ŔY��ł��Ă������̏o�Ȃ��Ƃ��͌���ɑ����^�ԂɌ���B���͂��������A�쐣����Ƀ��[���𑗂邱�Ƃɂ����B�܂��͎�ނ̂���Ɛi�����q�ׂĂ���A���̊Ԃ́u���߂��ɕ�炵�Ă݂�v���ɂ��ċ���������Ɠ`����B
�@�m�F�����������̂́A�u���߂��Ɂv�Ƃ����̂͋�̓I�ɂǂ̂��炢�̂��Ƃ��w���̂��낤�Ƃ������Ƃ��B���݂̎d���Ƃ̌��ˍ���������̂ŁA�m�[�g�o�b�������Ă����Ė�ɂ͍�Ƃ�����Ƃ��Ă��A�P�T�Ԃ����x���낤�B
�@���̓��̖�ɂ́A�P�T�Ԃł��\�����ƕԎ��������B
�w�T���������āA�Ƃɔ��܂��Ĕ_��Ƃ����ċA��l���������܂��B�����̂Ȃ��͈͂ő��v�ł���B���Ă̎��n�͂����I���܂������A���͏����ȃn�E�X�ő卪�┒�A�J�u�������Ă��܂��B����ł悯��x
�@���Ⴀ�A���Ђ��ז������Ă��������ƕԎ�������ƁA�ȍ~�̓��b�Z���W���[�ŋ�̓I�ȓ����⎞�Ԃ��l�߂��B���ǁA���̏T�̏T���ɍs�����ƂɂȂ����B
�@�ꏏ�ɏZ��ł���o�ɂ́A���x�͂P�T�ԂقljƂ���Ƃ��������āA���e�͐������Ȃ������B���݂��̎d���ɂ��ďڂ����킯�ł͂Ȃ��̂ŁA���������������邩�܂Řb���Ȃ��̂͂����̂��Ƃ��B
�����ڏZ���邱�ƂɂȂ���������z���ȂǂŖ��f�������邱�ƂɂȂ邾�낤���ǁA���̎��_�ł͉����b���Ȃ��B����ӂ�ȏ��ō���������ق����������Đ\����Ȃ��B
�@�����͓d�Ԃ��g�����Ƃɂ����B�Ƌ��͂����Ă��Ԃ͎����Ă��Ȃ����A�����^�J�[�ōs���ɂ��Ă��T���̓��̍����\���ł��Ȃ��B
�V�������~��čݗ����ɏ�芷����ƁA�T�����Ƃ����̂ɐ��w�ŃK���K���ɂȂ����B����Ă���唼�͂��N��肾�B�{���ɉߑa�������Ƃ���ȂƁA�Ђ��Ђ��Ɗ�����B
�@�{�b�N�X�V�[�g�ɍ����Ă������̎ߑO�ɂ́A�Ȃ��Ȃ��̃C�P�����������B�N�͎��Ɠ������炢���낤���B
�i����ς�ړ����悤���ȁc�c�j
�@�C�P�����Ƃ͂����A�l�̂��Ȃ��ԓ��ł��ꂾ���߂������ɂ���̂͗��������Ȃ��B������Ƃ��ɂ͂��������l�������̂����A���͂����A�����܂ŋ߂��Ƃ������ĕs���R�ȋC������B
�@����ł������Ȃ������̂́A�ނɂȂ�ƂȂ����o�������������炾�B
�i�N�������H�@�ǂ��ʼn���������c�c��ސ�H�@������A�����ƁA�����Ɛ́c�c�j
2017.3.7 up�@�u�����ĐU��Ԃ�v

�@�����A�s�v�c�Ȃ��Ƃɔނ��Ȃ��ړ����Ȃ��B
�@�Ԃ̑��l�Ƌ߂������ɂ��邱�Ƃ����܂�C�ɂ��Ȃ��l�����邯��ǁA���������^�C�v�ɂ������Ȃ��B
�@����ɁA����������C�ɂȂ�悤���B�Ƃ��ǂ��A���炿��Ǝ��̂ق����M���Ă���݂����ȁc�c�B
�@�������͌��ǁA�قړ����ɐȂ𗧂��āA�������ꂽ�ȂɈڂ����B����ł��A����Ă�����ς莋�����������B��������̎����������Ă������낤�B
�@30���قǓd�Ԃɗh��ꂽ�B�ړI�n�̉w����������A�i�E���X������Ă����̂ŃW���P�b�g�𒅂ĉו���������ƁA�ނ������悤�ɂ��Ă����B
�i���̗p������낤�B�n���̐l�H�c�c�ɂ͌����Ȃ��Ȃ��j
�@�~�肽�w�̃z�[���ɂ͐l�͂��Ȃ������B�w����������Ȃ��B�܂薳�l�w���B������ɂ͒��̖����킷�̂ǂ��Ȑ���������������B
�@���͔ނ��C�ɂ��Ȃ��ӂ�����āA���D���Ɍ������ĕ����o�����B
�u�Ђ���Ƃ��āA�ɐ삳��H�v
�@�ނɂ����Ȃ薼�O���Ăꂽ�B�����ĐU��Ԃ�B
�@�ǂ����Ď��̖��O��m���Ă���́H�@���͔ނ̊���܂��܂��ƌ��߂��B
�@�������c�c�N�������B�v���o�������Ŏv���o���Ȃ��B
�@���̂Ƃ��A���D���̌���������N�X�Ƃ��������������B
�u���݂܂���B�҂��܂����H�v
�@���x�͂�������U������ƁA�쐣�����D�̌������ɂ����B�w����쐣����̉Ƃ܂ł͋���������̂ŁA�d�Ԃ̓����ɍ��킹�ĎԂŌ}���ɗ��Ă����ƌ����Ă����̂��B
�u�����A�S�R�v
�u���A�s��ƈꏏ��������ł��ˁv
�@�쐣����́A���̉��ɂ����ނ����Ėڂ��ۂ������B
�u�Ȃ�A���鎞�Ԃ��킩�����狳���Ă�����Č����Ă���������Ȃ����v
�u����H�@���[���͂��ĂȂ��H�c�c��ׂ��A����ĂȂ������v
�@���̓�l�͒m�荇���Ȃ̂��H�@���͐쐣����ƃC�P���������݂Ɍ�������B
�@�Ɠ����ɁA�s��Ƃ������O�ɂ������������o����B�c�c�s��A����H
�u����A�Ђ���Ƃ��Ďs�삭��H�v
�@�����̂��܂�A�P�I�N�^�[�u�͍��������o���Ă��܂��B
�@�ނ͏��w�Z�̓������������B������Ƃ�������ŁA�o�Ȕԍ����ʼn����ƈꏏ�ɂȂ邱�Ƃ����������B
�u�����A������Ƒ҂��āB�ǂ��������ƁH�v
�@���x�͐쐣���ۂ���Ƃ���B
������
�@�s�삭��Ƃ͒��w�Z�܂œ����w�Z�ɒʂ����B
���w�ɓ����Ă���͐��k���������Ă��܂������킹�邱�Ƃ͂Ȃ��Ȃ�������ǁA���A���炢�͂��Ă����B
�@�ނ́A�m���ɓ��������͐����Ă����B�ł��A�n���������B�n���Ƃ������A�������������B
�@���̔��ʁA���͒��w�ɓ�����������o�ւ̔����ŃI�V�����ɖڊo�߁A�u���������v�̑f�n�������Ă������B
�@�m���Q�N�̂Ƃ��������Ǝv���B���́A�ނɍ������ꂽ�B
�@���������͔ނ�F�B�ȏ�̑��݂Ƃ��Č���ꂸ�A�f�����B
�@�I�V�����ŗ��������ł��鎄�̔ނ́A�݂�Ȃɐl�C�̃C�P�����łȂ�������Ȃ��B�����l�ł͂Ȃ����ꏏ�ɂ��ċC�y�ȑ���ł͂��邯��ǁA�s�삭��݂����ɖ��������j�q�ƂȂ�ĕt����������]���������Ă��܂��B�������A����Ȃ��Ƃ܂ł͌���Ȃ���������ǁB
�@�����f�����̂����������Ɏ������̊Ԃɂ͋������ł����B���m�ɂ����A�ނ����������悤�ɂȂ����B�ł��A�����Ēǂ�������������ł��Ȃ��������A�Ƃ��ɉ������Ȃ������B
���̌�A�s�삭��͕��ɗ͂����n�߂��悤�������B�����āA�n���ł̓g�b�v�̐i�w�Z�ɓ��w�����B
2017.3.8 up�@�u�܂������₾�Ƃ͌����Ȃ��v

���Ǝs�삭��́A�쐣���^�]����y���S���̌㕔���Ȃɕ���ō������B
�u�����͍L���㗝�X����̓����Ȃ�ł���B�ɐ삳��̏����w�Z����̓������������Ȃ�āA���R���Ă�����̂ł��ˁv
�@�쐣����͌������B�s�삭��́A�쐣����ɗ��܂�ďT���ɂ悭��`���ɗ��邻�����B
�i�C�P�����̓C�P�������ĂԂ̂��c�c�ǂ������i�D�����Ȃ��j
�@���̂ق��́A��������ȂƂ�����肪�C�ɂȂ��Ă��܂��B
�i�s�삭��A����ȂɊi�D�悭�Ȃ������t���Ȃ���悩�����ȁ`�j
�@�Ȃ�āA��k���ۂ��v������������B
�@�쐣����̉Ƃɂ͒j����l�A������l�����łɏW�܂��Ă����B�������Ƃ��n�߂Ă����炵���B���͋x�ݎ��ԂƂ������ƂŁA�����ł���������ł���B�쐣����̒m�荇����A�m�荇���̒m�荇���ŁA�S���A��s���������Ă����������B
�u�r�j�[���n�E�X�͉Ƃ̗���ɂ���܂��B��ꂽ�炢�ł��o�Ă��āA�x��ʼn������v
�@�쐣����͂����������Ă��ꂽ�B
�@�����܂ō�Ƃ��āA�[�H�ɂȂ����B�y�Ԃɒu�������ւŁA�쐣���n���̖��L�m�R�A�����Ȃǂ��Ă��Ă����B�������A���ɂ�����o���Ă��ꂽ�B
�@�ݖ���h�����\�ʂ����ւŏĂ������ɂ���́A�M�����Ȃ����炢�������������B���̓A�c�A�c�Ńp�����Ƃ��Ă��āA���͂������Ƃ��Ă���B�S����o�����߂ɁA�킴�킴��x��₵���������B
�@�݂�Ȍ��X�ɂ��������A���������Ƒ����Ȃ��炲�͂��H�ׂĂ�������ǁA���̐S�͍��ЂƂ���Ȃ������B
�@�����̔_��Ƃ͊m���Ɋy���������B�y�ƐG�ꍇ���č�Ƃ���̂��A����Ȃɖ��S�ɂȂ�邱�Ƃ��Ǝv��Ȃ������B
�@�����炱���A�������͐[�܂����B�܂�Ȃ��Ƃł�������A�����ƊȒP�ɓ������o�����Ƃ��ł����̂ɁB
�@���͊ʃr�[������ɂ��ė���ɏo���B
�@�����������ꂢ�������B��C�����݂����Ă��āA����Ė{���͌����Ŗ��邢���̂ȂƂ킩�����B
�@�w��ō����މ��������̂ŐU��Ԃ�ƁA�s�삭�߂Â��Ă���Ƃ��낾�����B
�u������Ƙb���Ă��������ȁv
�u�������v
�@�{�S�ł͏����ْ���������ǁA�܂������₾�Ƃ͌����Ȃ��B
�u�܂�������ȂƂ���ňɐ삳��ɉ�Ȃ�āB�{���ɋv���Ԃ肾�ˁB���Z�ɍs���Ă���͑S�R���Ȃ��������v
�u�������ˁv
�@�B���ɂ��Ȃ����B���w����Ƃ͂����A�t��������Ƃǂ�������Œ�������̂��A�悭�킩��Ȃ��B
�u���͂��A���Z�ɂȂ����������x�ɐ삳��ɍ������悤�Ǝv���Ă��v
�@�G��Ă����̂��ǂ����킩��Ȃ��Ƃ���ɂ����Ȃ�荞�܂�Ĉ�u�S�������ˏオ�������A�������u�����ŁA���Ƃ͂������Ċy�ɂȂꂽ�B
�u�U������Ă��炦��悤�ɕ����撣���āA���ꂩ�猩���ڂ������Ȃ�ɖ����āB�ł��A�ɐ삳��͂����Ɣގ���������������A�Ȃ��Ȃ��`�����X���͂߂Ȃ������B���̂����ɉ��̂��Ƃ��D�������Č����Ă����q������āA���̎q�A�����q��������ŕt�������悤�ɂȂ��āA��w�̎��������āc�c�v
�@�����A�����̂���܂ł��ȒP�ɘb�����B�u���������v�Ƃ���簐i���Ă������̂��Ƃ�A���߂̎����ɂ��Ă͂������ɏڂ����͘b���Ȃ��������B
�@�b���Ă��邤���ɐ̂̋C�y������݂������Ă��āA���A�������Ă���̂��A���ꂩ��ǂ��������̂��Ƃ��������Ƃɂ܂Řb�͋y�B
2017.3.9 up�@�u�^���H�v

�u���͉��A�������Ă��ˁv
�@�s�삭��́A�������グ�ď����������������B
�u���܂ł��ނ����ɓ����Ă��āA����Ȃ�̌��ʂ����Ă��āA�ł����̂܂܂����Ƃ���𑱂��Ă����̂��A����ł����̂��Ȃ��Ďv�����Ƃ��ɁA�쐣���ސE���Ă����ŕ�炵�n�߂��B�b�����͂����ƕ����Ă������A�T���ɂ͉Ƃ̃��m�x�[�V��������`���ɗ����肵������ǁA�Ȃ��ǂ�ǂ�A�܂����Ȃ��Ă��Ă��v
�u�A�܂������āA�����H�v
�u�l�̖��ɒ���������̂�������āA�������������Ə[����������B���̎d���́A������L���ɂ͂��邯��ǁA���ƒ��ڂȂ����Ă��邩�Ƃ�������Ȃ����炳�v
�u����A�킩���v
�@���ׂĂł͂Ȃ�����ǁA�����𗣂�Ă������ŕ�炵�Ă݂����Ƃ������R�ɂ́A����ȋC�������������Ă���B
�u�����ˁA�������Ă���B�����Ń��C�^�[�̎d��������̂��y�������ǁA���������Ƃ���ŕ�炷�̂ɂ������������āc�c�v
�u�������B�ȂA�^���݂����Ȃ��̂��������Ⴄ�ȁv
�u�^���H�v
�u����B�D���Ȑl�ƍĉ�āA�ꏏ�ɐV���Ȑl���ɓ��ݏo�����Ă����̂��c�c�����ɐ삳����ڏZ��������炾���ǁv
�u�ꏏ���āc�c�Ȃ�����A��������݂�������Ȃ��v
�u�͂́B�����Ȃ肻��Ȃ���͂Ȃ��������ǁA��ŐU��Ԃ��Ă݂��獡���̂��Ƃ����ǃv���|�[�Y�������̂��Ȃ��Ďv���̂����ˁv
�u������Ƃ�����ƁB���A����Ȃ����܂��ȃv���|�[�Y�̓C���v
�u�����A�v���|�[�Y����Ȃ炿���Ƃ��������ǂˁv
�@�����܂Ō����āA�������͖ق肱�B���������̘b�������ƂɁA������Ȃ����l���ďƂ�Ă���̂���C�ł킩�����B
�u������Ƃ��̂ւ�A�����Ȃ��H�v
�@�s�삭��ɗU���āA�������͉Ƃ̗��傩�珬���ɏo���B��̊�����ꂽ�c��ڂ�������Ő���ɒ��݂����ɂȂ��Ă���B
�@�����Ȃ���A�s�삭��͂������R�Ɏ��̎��������B���͐U�蕥�����Ƃ͂����A�w��ɏ��������͂����߂��B
�@�Ђ���Ƃ�����A����͍ō��́u�V���Ȑl���̓��ݏo�����v��������Ȃ��B���ނ̂��Ƃ��A�Y����邩������Ȃ��\�\�B
������
�����ɖ߂�ƁA�܂��͗��܂��Ă������[���̕ԐM��Еt�����B�쐣����̉Ƃɑ؍ݒ��ɂقƂ�ǕԎ������Ă�������ǁA������Y�t���Ȃ��Ƃ����Ȃ����̂ȂǁA�܂����ʂ��͎c���Ă����B
��Ƃ��Ă���ƁA�|���Ǝ�M���������������B
�@�m�F����ƁA�j�c���炾�����B
�w���̘b�A�ǂ��H�@�悩�������x�b���Ȃ��H�@�E�`�ɗ�����V�������x
�@���Ȃ݂ɁA�j�c����ƉƂ��s��������̂͒��������Ƃł͂Ȃ��B�ł����킹����ɂ��ꂼ��̉Ƃ��g�����Ƃ�����B�����t������������A����Ȃ��Ƃ�������O�ɂȂ��Ă��܂����B
�@����ȕt���������A�����ڏZ������Ȃ��Ȃ��Ă��܂��낤�B
�@�����l����ƁA�V�тɍs���邤���ɍs���āA�b���������Ă��������C�������B
�@�\����m�F�������Ɨ����̖邪�Ă����̂ŁA�Ƃ�K�˂邱�Ƃɂ����B�j�c����͗����Ɋւ��Ă͎B�e�����ł͂Ȃ����邱�Ƃ��D���ŁA���̖��̍D�݂��킩���Ă���B������܂��A���N���Ԃ��Ƃ��ɂ��Ă������炾�B
�@���̓��́A�p�X�^�������đ҂��Ă��Ă��ꂽ�B�\�[�X�͓��h�q���s�����Ƃ��������A���r�A�[�^���B
�@���̓p�X�^��H�ׂȂ���A�����ɁA���͐쐣����̂Ƃ���ɈڏZ���邱�Ƃɋ���������̂��Ƒł��������B
2017.3.10 up�@�u���������v
�@�j�c����́A����قNj����Ȃ������B
�u�܂��A�ɐ삳��͂����ꂻ���������Ƃ������o���Ǝv���Ă�����v
�u�܂��Y��ł�����ǂˁv
�u�Ƒ��͂Ȃ�Č����Ă���́H�@����������Ƃ�����傪����Șb�ɂȂ邾�낤���A������߂��ɂ���l�̃A�h�o�C�X�����ق���������Ȃ��v
�u�Ƒ��c�c�I�v
�@�^����Ɏv�������̂́A�o�̍�̊炾�B
�@���e�Ƃ͗���ĕ�炵�Ă����Ԍo���A������A�h�o�C�X�Ƃ��ėL�p�����Ȃ͎̂o�̈ӌ����낤�B�̂قǁA�������a�������Ă��Ȃ��B
������Ƙb�������@�������Ȃ��B���͂��������o�ɑ��k�����B�����ԁA�R���v���b�N�X������Ă������Ƃ͂������ɘb���Ȃ������B�ł��A��ɂ��������������Ƃ͐����Ɍ������B��������܂��Ɉ��������Ă��邱�Ƃ��B
�o�̓����́A���ɂ܂��Ƃ��������B
�u�d���ɂł������ɂł��A���f�������ׂ����ƈȊO�Ŕ��Ă���̂Ȃ�A���̔�ꂪ�����Ă��猈�߂��ق���������B�ق��̊���ɐU����ƁA���������f���ł��Ȃ��Ȃ�v
�@�������ɗ��n�̉@���炵���A�Ƃ������炻��͂���ŕΌ��ɂȂ肻�������ǁA�Ƃɂ����|���X�p���Ɗ������悤�ȕԓ��������B
�m���ɐ́A�������]�܂Ȃ��܂܁u���������v�ɂȂ����̂��A�ׂɗ����������Ƃ�����]����ł͂Ȃ��A�o�ւ̔����Ƃ����u�ق��̊���v�������������B�I�ڂ��Ǝv���ق��̓����I�ׂ��̂ɁB�����œ�������āA�{�ӂł͂Ȃ������������N�������B���ǁA������������������Ă���B
�u���肪�Ƃ��B���o�������āA����ɂȂ�ˁv
�u���ɗ��Ă��̂Ȃ�悩�����v
�@�o�͏��Ԃ��Ă��ꂽ�B
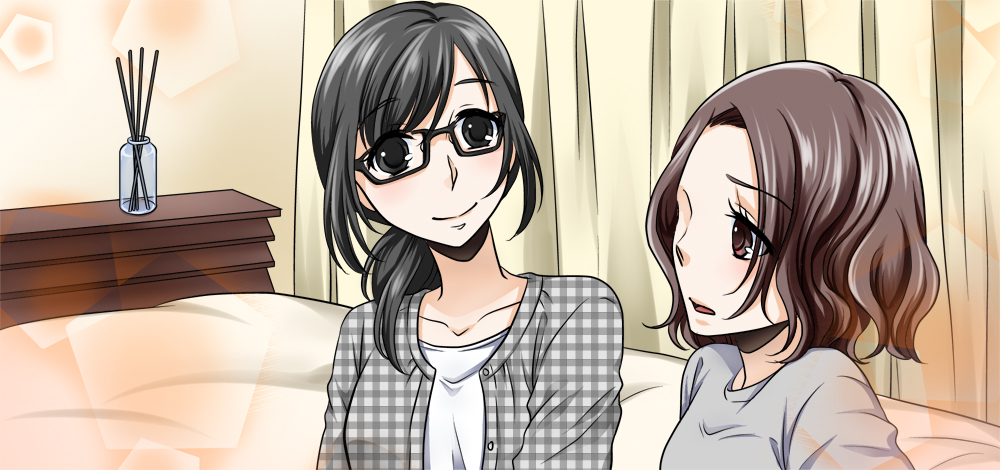
������
�����̏��́A�܂������Ă��Ȃ��B
�s�삳��̂��Ƃ��A���ނ̂��Ƃ�Y��Ă��炿���ƃX�^�[�g���������B���͒j���Ƃ��ċ����䂩��Ă���Ƃ������́A�V�������Ƃ��n�܂郏�N���N���ɖ�Ⴢ��Ă��邾���Ƃ����C�����Ȃ����Ȃ��B
�j���[�g�����Ȏ��������߂����B�����Ɍ��f������̂͂�߂āA���͓����ŁA�K�v�Ƃ��Ă�����Ă��邱�Ƃ����悤�B���̌�œ������o���̂ł��A�x���͂Ȃ����낤�B28�Ƃ����N��ɏł�����邯��ǁA������Ƃ����ē������}���ł͌�����������B
���͐쐣����Ǝs�삭��A����ɏj�c����ɘA�������āA��͂�������������Ŋ撣���Ă݂邱�Ƃɂ����Ɠ`�����B
�s�삭��́A����̂����������̉��Ȃ̂�����A�����ڏZ���Ȃ��̂Ȃ玩���������͏T���̎�`�������ɂ���ƌ������B�����ɁA�u�������ʔ̃T�C�g�^�c�v�Ȃ�Ďd��������̂Ȃ狻��������A�������ꖇ���݂����Ƌ������������B��`�Ɋւ�肽���Ƃ����B
���ہA�s�삭��͂����Ɏ���āA��`�S���̈�l�ɂȂ����B�Ȃ������āA���������Ƃ��ɑ��͋����B
������
�@���ꂩ���Q������\�\�B�x�d�Ȃ����c���o�āA���悢���悪���M�����B�d���͎v�����ȏ�ɖZ�����A�I�d�߂��܂ł����邱�Ƃ���������イ�������B
�@����ȂƂ��A����n�v�j���O���N�������B

|
|
���N���b�N�œ��[���Ă��������B |
��l�C�A���̖�����Ăсc�I








































